| 静岡県浜松市 市議会議員 鈴木めぐみホームページ | |||
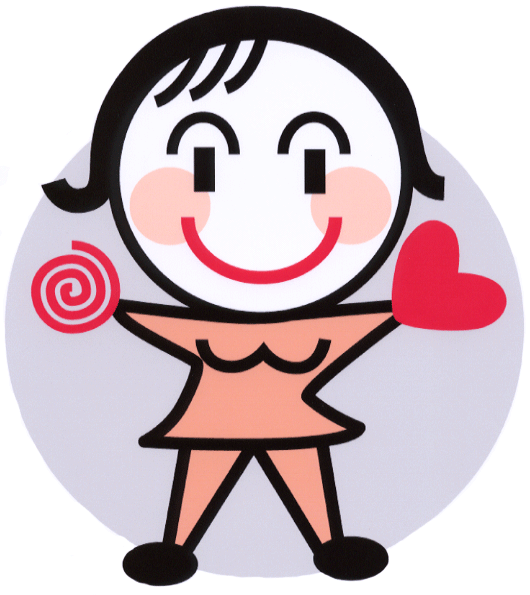 |
|
||
| 右手にネットワーク・左手にハート 浜松HAPPY化計画 | |||
|めぐみの浜松HAPPY化計画ブログ|めぐみリサーチコンテンツ| |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
 |
「子どもたちが安心して過ごせるために」 放課後児童会への提案書と回答 「エンゼルプランの見直し」に 浜松市の現状は・・・ |
| だから提案!2001.7.28 | |
| 浜松市の放課後児童会は、公設民営で設置された児童の放課後対策。浜松市内全小学校(静岡大学付属小を含む)65校中52校で設置率80%と数的には充実しているように見える。しかし本当に需要数を満たしているのだろうか。 放課後児童会数と需要予測から、なお約500人の需要が予測される。児童会によっては、定員オーバーしていたり、入れずに待機している人もいる。中途ではさらに入会できないのが現状である。 浜松市の35才からの女性の労働率は、全国平均より上回っていることから、保育園に入園していなくても子どもが学齢期に働く母親が多いことが推測できる。また最近は、私立幼稚園の「預かり保育」を利用して働いているケースも多い。 児童会の現状と女性の働き方から、全国と比較しても浜松市の放課後の児童対策の必要性は高い。放課後児童会公設民営の充実・民間学童(保育園・ NPOを含む)の活用を考えると共に、子どもの放課後の生活と安全を図る策を考える必要がある。 |
|
|
|
|
| 放課後の子どもたちが安心して過ごせる浜松に | |
| 浜松市では平成10年3月「はままつ友愛のエンゼルプラン」が策定され、“安心して子育てができるまち浜松”に向けて、様々な取り組みが進められています。 その一環として、「浜松市放課後児童会」の開会時間の延長、開設場所の増設などが実施されるようになりました。 このような状況のなかで、放課後の児童対策は、数量的な問題から、より質の高いサービスへと求められるようになってきています。現在の放課後児童対策が本当に親たちにとって安心して働き続けられるサポートになっているのか、また子どもたちが安心して放課後を過ごしているのかなどについて、「浜松市放課後児童会」に入会している方、及び入会していない方を対象にして実施した調査結果をもとにしています。 また調査を実施するだけでなく、今年2月にはあんふぁんて浜松・働くママの会と共同して情報交換の会を開き、さらに7月にはアンケート結果をもとに、あんふぁんて浜松・働くママの会の方々と一緒に意見交換を行なってきました。 そして7月28日、浜松市へ「放課後の子どもたちが安心して過ごせる浜松に」の提案書を提出し、担当課である児童家庭課から10月22日その回答をいただきました。 |
|
|
|
| 私たちの提案/2001.7.28 | 児童家庭課(浜松市)の回答2001.10.22 | |
| 内閣府の男女共同参画会議『仕事と子育ての両立支援策の方針に関する提言』(平成13年6月19日)の4点目「必要な地域全てに放課後児童対策を」をもとに、浜松市での現状の分析から、放課後の子どもたちが安心して過ごせる浜松に以下の6点を提案します。 ・. 放課後の学童のための居場所を確保 ・. 時間的にも保育所と同等のレベルを確保 ・. 公的な責任の下に民間の活用を図る ・. 子どもの発育に役立つプログラムを提供する ・. 施設に関する必要な情報を提供する ・. 子どもの安全を守る |
当市の放課後児童会は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象に小学校余裕教室等で、公設民営方式により、実施しております。 児童会の開設状況は、13年度に2箇所増設し、小学校内に28箇所、公民館内に17箇所、なかよし館内に2箇所の47児童会を開設しております。 また、 開設時間については、下校時から午後5時30分までとなっていたものを、平成13年度より30分延長し午後6時までと充実を図ったところでございます。 今後も余裕教室を活用し、全小学校(64校)への開設に向けて整備を進めてまいりたいと考えております。 |
|
| ・. 放課後の学童のための居場所を確保 |
1. 放課後の学童のための居場所を確保について |
|
| ★必要とする全ての子(障害児を含む)が、ホッとできるくつろいだ居場所を確保する。 ●市内の全小学校に児童会を設置すると共に、市立幼稚園や空き教室の活用も検討する。 ●放課後児童会の入会が必要であるとした保護者の判断を尊重する。
|
今後も、保護者の要望や地域の実情を踏まえた中で、 余裕教室の状況を勘案しながら全小学校に開設してまいりたいと考えております。 |
|
| ・. 時間的にも保育所と同等のレベルを確保 |
2. 時間的にも保育所と同等のレベルを確保について |
|
| ★保育園で行なっている19時までの保育や長期休暇保育と同等レベルを確保する。 ●各児童会ごとに希望を調査し、延長を希望する親が多いところは予算をつける。それなりの適当な利用者負担も求める。 ・アンケート結果から、ニーズに合うなら¥1000〜¥2000程度なら追加料金を払っても構わないという声が多い。ただし利用者負担に際しては、兄弟割引き、母子家庭などの市民税非課税世帯などの減免措置も必要。 ※母子家庭などへの減免措置について 公設民営の児童会がニーズに合わない以上、民間学童や保育園など民間の事業所に頼らざるを得ない。そうした場合の保護者の負Sは大きくなるので、一時的に支払っても後で保育料減免措置が執られて、保護者に直接還付されるようにする。 ●働き方に合わせた開設方法とする。 ・ 卒園から入学までと、春夏冬の長期休暇にも開設する。 ・ 開始終了時間を保育所と同等にする。 ・ 日数を増やす。 ・ その児童会ごとに保護者会などで必要を検討し、その児童会のその時のニーズに合わせた方法で行なう。
|
開設時間は、13年度より30分の延長を行い午後6時 までとしましたので、当面現体制で対応してまいりたいと 考えます。 長期休暇中の開設については、運営経費増加に伴う財源 の問題等課題解決に努め、前向きに検討してまいりたいと 考えます。 |
|
| ・. 公的な責任の下に民間の活用を図る |
3. 公的な責任のもとに民間の活用を図るについて |
|
| ★働く女性のサポートの点から児童会のあり方をとらえ、保護者の必要に応じてサービスを選べるように公的責任のもとに仕組みをつくる。 ●公的な責任を明確にする。 公的な責任はどこまでなのかを明確にし、どこの児童会でもベースは守られるようにする。 1. 市が保育園と同様に入会申込書を行政窓口で受け付けて、申し込みの時点から公平にする。 2. 子どもが放課後あるいは長期休暇の1日を過ごす上での、生活環境を整備し、公的責任においてチェック項目に沿って点検する。 3. 放課後児童会への相談や意見を受け付け、よりよい放課後児童対策に活かしていく。 4. 指導員は、豊富な経験だけでなく、責任を持った対応をしてもらうためにその立場を明確化し、またそれに見合った評価がされるべきである。また、指導員の質の向上のために、指導員の採用基準と求人をオープンにし、研修を行ない、評価システムを作る。 ●放課後児童会の公設民営のよさを活かす! 保護者と指導員、その地域や関わる人のニーズに合った、独自のスタイルで、柔軟に運営ができるような組織・仕組みにする。全児童会一律でなくてよい。 1. 地域のニーズ、利用者のニーズに合わせて、時間の問題や土曜日の開会を考える。少人数のニーズにも応えられる仕組みも考える。 2. 関わる全ての人と民主的に決める。 3. 保護者・地域のネットワークの中で、児童会の中だけでは解決できない問題を、相互扶助的に解決する仕組を作る。そのために情報交換する機会と保護者がコミュニケーションをとる機会が必要。 ●民間学童や意欲のあるNPOの活動を支援する。
|
児童会は、地元の育成会が自分たちの特色を生かした運 営を行っております。 今後も引き続き、育成会と協力して、児童会活動の充 実を図ってまいります。 |
|
| ・. 子どもの発育に役立つプログラムを提供する |
4. 子どもの発育に役立つプログラムを提供するについて |
|
| ★既存の施設や民間・地域からのプログラムの提供と、それを活用できる仕組みをつくる。 ●科学館、子ども館(平成13年度秋オープン予定)、博物館、美術館や民間からもプログラムの提供を受けたり、1日移動教室(博物館、絵本読み聞かせ等)を活用する。 ●地域の人材資源を活かす。公民館等で学んでいる人たちや、中高生ボランティアに入ってもらう。 ●長期休暇・土休日対策として、全児童を対象に夏休みに学校を1週間程度地域開放し、多様なプログラムを組み合わせて、仮称「地域子どもウィーク」のようなものも行なう。
|
児童会では、家庭的な雰囲気の中で、基本的な生活習慣 や遊びを通じての自主性・創造性を育む指導を行っており ます。これからも、各種情報等を活用するとともに、地域 の人たちの協力をいただきながら児童会の充実を図ってま いります。 |
|
| ・. 施設に関する必要な情報を提供する |
5.施設に関する必要な情報を提供するについて |
|
| ★入会者、未入会者、サポートしたいと思っている人たち、誰にでも分かるように情報を提供する。コンセプトは“地域で育てる放課後の子どもたち”!! ●入会保護者に対して、充分な説明と情報を提供する。 ・ 児童会と保護者の連絡・関わり方を、明示する。 ・ 会計報告などの情報を公開する。 ・ 保護者会とは何をするところか、育成会とは何をするところか、また行政(児童家庭課や教育委員会)との関わりはどうなっているのかを、明確にする。 ●保護者へ「どのように放課後を過ごさせるか」の情報を提供する。(市としてできること!) @ いつ:11月の入学前健診の時 @ どのような内容か: 1. 公的サービス(放課後児童会、ファミリーサポートセンター)・民間サービス(民間学童保育、保育園等)、NPOなどの情報を提供する。 2. 困った時の対処法 3. 放課後児童会とは、どのような組織か。その歴史や仕組み、公設民営等の情報・資料提供をする。 4. ホームページで分かりやすい情報を流す。(地図、場所、条件、時間、料金等) ●各児童会からの情報を各方面に提供する 1. 各放課後児童会が、毎月でなくとも季刊でもお便りを発行する。放課後児童会の活動内容や、時間の変更のこと、指導員のこと、行事報告やふだんの様子など。まずは、入会者に配布。 2. そのお便りを地域で回覧する。 3. その地区の学校で実家庭に配布する。 4. その地区の幼稚園や保育園にも情報を提供する。
|
児童会設置地域の小学校入学説明会において、放課後児 童会入会について情報提供をしております。 なお、在籍保護者に対しましては、児童会活動の情報提 供が、円滑に図られるよう育成会の指導に努めてまいりま す。 |
|
| ・. 子どもの安全を守る | 6. 子どもの安全を守るについて |
|
| ★組織や会としてリスクにどう対応するのか、安全を守るために各児童会で話し合うと共に、行政としても対応策をマニュアル化する必要がある。 ●外側の安全面への対応として 児童会に行くまでの道のりの安全性が問題となっている。交通事故や事件(ちかん、誘拐、殺傷など)等への対応を具体的に検討し、また子どもも身を守るためにCAP※のプログラムを学ぶ。 ※ CAPとは、(Child Assault Prevention 子どもへの暴行防止)という意味です。CAPプログラムは、子どもたちの人権意識を育てる事によって心を傷つける暴力、体を傷つける暴力、性的な暴力から身を守る方法を教えるプログラムです。 ●内側の安全面への対応として 1.保護者と児童会が連絡を取り合う。(困ったことや早退の時はどうするのか等) 2.相互の話し合いの場が必要。
|
児童会は、浜松市放課後児童会に関する要綱に基づき、児童の健全育成を図るため運営しております。 帰宅時は、確実に保護者に引き渡し、安全確保につとめています。 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ◆◇ 鈴木めぐみ事務所 ◇◆ Webサイトについて |
〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山二丁目5-10 TEL・FAX(053)431-1511 E-mail:megumi-hp@megumi-happy.net |
Copyright (C) 2000 By Megumi Suzuki Office (JAPAN) All rights reserved.